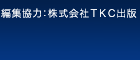ホーム
> [飯塚毅博士の言葉] 自己探求の言葉-2
自己探求の言葉-2
心の動きを看視せよ
心の動きというものは面白いものです。何しろ、形がないものですから、その動きそのものを看視する人も、余りいないようです。殊に、古来いわれている「真の己」というものは、自分の主体を指していますから、手がつけられない。何よりも、己の主体は、人間が客観化できない性質のものですから、困りものです。
自分が客観化できない世界に、己の主体がいる、というこの事実が、踏み越え難い関所となっています。己の主体というものは、冷暖自知する以外にアプローチの方法がない。冷暖自知というのは禅語で、冷たいとか、暖かいとかは、自分の身で体験する以外には分らない、ということです。そういう性質のものですから、古来、真の己を知った者は稀だ、ということになります。釈尊がこれを知り尽くすのに6年もかかった、というのも、尤もだと思う次第です。
さらに困ったことは、この形のない心の動きには、習慣がつき易い、ということです。目の先30センチぐらいの所に、心が常に集中する、という生活習慣の持ち主には、仲々、地平線の先は見えません。心のそういうくせは、手で触るようには、知られませんから、厄介です。知られないから、自然にそういう習慣が身についてしまうのです。
仏教の方では、これを薫習(くんじゅう)又は習気(じっけ)といいます。この薫習又は習気から脱け出すことが、悟りへの決め手だといわれます。何しろ、自分の体に浸み込んでしまった心の動きのくせですから、ちょっとやそっとでは、拭い去れないのです。われわれ凡人の心には、この薫習というものが、頑固にへばりついています。心の生活の中で、自分の薫習との戦いを意識するようになったら、その人は、悟りの一歩手前にきている人だ、といえましょう。しめた!ということです。
この薫習を抜け出す方法は、何よりも自分の心の中を看視する態度が、執れるか否かでしょう。看視する態度が執れるようになったら、次は、心の本来の姿に、常時安住する工夫を積むことです。心の本来の姿に常時安住するというのは、心が無味、無臭であって、相が無く、而も十方に通ずるものだ、ということをよくよく知って、そう知られた実体の中に、心の常時の回帰点を持つ工夫を繰り返す、ということです。
それは驚くほどの平穏、安楽の世界を入手できたことを意味します。ストレスなどというものが全く無い世界ですから、即ち、安楽の世界の出現となります。
ゲーテは、エッケルマンとの対話をやった晩年期に、自分が常時、心の回帰点に戻っていることを告白しています(『ゲーテとの対話』エッカーマン)。ゲーテは、無心を、己が心の回帰点としていたのですね。ゲーテに限らず、人類史上で、真に偉大な人生を送った人は、無心への回帰を常時行っていた人だったことが想起されます。
私の師匠の、雲巖寺の植木義雄老師も、紛れもなく、その一人でした。彼はその修練が綿密厳格を極めていましたから、瞬間的に無心に回帰しており、而も、無心に固執しませんから、融通無碍なんですね。いかにも自由自在に生きた、というお方でした。97歳までも、長寿を保ったということは、生きてゆく上で世のいわゆるストレスが溜らなかったことだ、と見てよいでしょう。外見上どんなに多忙であっても、年中、休息しているような状態ですから、芯から疲れてしまう、という生活は無かった、と私には見えました。
さて今回、私は、心の動きについて、語り始めました。その真意は、人が余りにも、己が心の動きを看視しない、という状態にあることを嘆かわしく思っているからです。特に将来ある若い人達が、膠で固めたように、その心が薫習でかためおおわれていて、自由を得ていない、という状態にいることを嘆くからです。目先の現象に、自分の心を住著させてしまっている、青年達の心の姿勢を嘆かわしく思うからです。人生は一度しかないのです。だったら、その人生を、自由自在に生き抜くべき、ではないのでしょうか。(『自己探求』飯塚毅著・TKC出版)
前ページ 1
2 3 4
次ページ
(2/4)