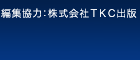ホーム
> [飯塚毅博士と私] 飯塚毅博士と私-5
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
飯塚毅博士と私-5
 (い)
(い)
朝日新聞社社友 伊波新之助
私が飯塚毅名誉会長にはじめてお目にかかったのは昭和40年代だと思うが、ご令息で現在の株式会社TKCの社長である飯塚真玄氏と友美乃夫人の結婚式の席である。場所は北鎌倉・円覚寺の大方丈。導師は真玄氏の恩師・朝比奈宗源老師であった。
私が忘れられないのは祝賀の席で毅氏の禅友である下野新聞の社主氏が漢詩でこの結婚式を祝い、最後に大きく「いいィ」と方丈の隅々にまで響くように声を発したことである。これには列席の老若は揃って腰を抜かしてしまった。「 (い)」とは禅語辞典によれば主として注意を促すときに発する大声だそうである。
(い)」とは禅語辞典によれば主として注意を促すときに発する大声だそうである。
禅宗では教えを挙揚する漢詩を偈(げ)とか頌(じゅ)と呼ぶが、社主氏は挙式を祝う偈を自らつくって唱え、この日の嬉しさを「 (い)」に奔出させたのだった。
(い)」に奔出させたのだった。
故毅名誉会長が那須・雲巖寺の植木義雄老師に参じて禅の道を探求されたことは遺著『自己探求』(TKC出版)などを通じてよく知られているが、その時に同じ寒さに震え、同じ粥を啜り、共に蚊に喰われた仲間が社主氏だったのではないか。
親鸞上人は悩んだ末に比叡山を下り、法然上人の膝下に参じて救われた。その救われた歓びは「もし法然上人にだまされて念仏し地獄に堕ちても決して後悔しない」という信念にまで高まった。禅宗は浄土門よりさらに師弟の関係を重視する宗派である。同じ釜の飯を喰った関係は何物にも代え難い親しさを生む。名誉会長と社主氏らの義雄会下(えか)の親しい語らいを脇で拝見していて、私はえもいわれぬ和やかさを感じた。
その後、私がTKC全国会の存在を知るようになると、今度は全国会創立前後の「とにかく会長に随いて行こう」という空気があたかも両上人の間に生まれた強い信頼関係のように思われた。
名誉会長の密葬も同じ円覚寺で行われたが足立慈雲管長は自利利他の行に一生を捧げられた故人を送るにふさわしい偈を述べられたあと、何と「 (い)」の語を発せられたのである。私の心の中にはこの2つの「
(い)」の語を発せられたのである。私の心の中にはこの2つの「 (い)」がいつまでもこだまして名誉会長の利他行を勧める声となって響き続けているのである。
(い)」がいつまでもこだまして名誉会長の利他行を勧める声となって響き続けているのである。 (飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』より。肩書きは2005年7月当時)
(飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』より。肩書きは2005年7月当時)
前ページ 1
2 3
4 5 6
次ページ
(5/6)