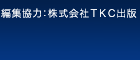ホーム > [飯塚毅博士と私] バンガード対談 > 命懸けの行・財政改革-6
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
命懸けの行・財政改革-6
日本の経済力を支えるのは勤労者だ
飯塚そう。例えば、こんど通達の改正で、養老保険の保険料でさえ、一部は損金として認めるということですが、これは驚くべきことなんだ。誰が正しい意味の所得計算ができるのか――。これはね、メッチャメチャな理屈なんですよ。世界に例がないんです。
中曽根うーん。でも、日本でも「所得のあるところに税金あり」というのが、原則じゃないんですか。
飯塚いや、そうじゃあないんです。それから「所得」という言葉は、危険なことばなんですねえ。
中曽根「収入」ですか――。
飯塚そうそう。所得というと、われわれは普通、課税所得を考えます。収入となると、所得と関係ない。収益は全部、収入ですから。
この点、アメリカの場合は、要するに、収入が一定水準以上であった場合には、みな、申告書を出す。その一定規準いうのは、時代の流れによって、何年かごとに改定されるわけなんです。ですから、アメリカの場合は、税の申告件数が年間に約3億件。
日本の事業所総数は、およそ510万ですが、そのうち事業所得の申告をしているのは250万ぐらい。
中曽根うーん。
飯塚ええ。たまげたもんですよ。
ですから、例えばね、大臣、俺には所得はないんだといえば、どうにもならない。もう1つは帳簿記帳の義務がない。そういうところに脱税容認というよりも、むしろ、脱税促進体制があるといえるんです。
そうした“脱税のうま味”がなければ、国民の活力がなくなっちゃうだとか、自由主義経済は成り立たなくなるという議論があるようですがね、これはとんでもない。なにを言ってるんだ、というんです。
中曽根そうですねえ。
飯塚はい。日本の経済的なパワー、力というものは、そうしたごく一部分の脱税階級の人間が形成しているんじゃあないんです。
さきほども言いましたように、その大部分がサラリーマンと誠実真剣な経営者たちですよ。このことは、何度いっても言いすぎではないんです。
中曽根あの、シャウプ勧告があったあたりでね、みな、青色申告制にしておけばよかったという意見もありますねえ。税率を安くして、正直に税を申告すれば、これは公平ですから……。
飯塚ズバリ、です。
国税庁長官だった磯辺律男さんと対談をやった時に「乏しきを憂えず、等しからざるを憂う」といっておられましたが、まさに、その通りだと思いますね。
中曽根ああ、いい言葉ですね。
飯塚そうでしょ。私も、この言葉は大好きです。それにしても、大臣はいつまでもシャープですなあ――。
これは大臣にも話したことですが、大臣が政界にデビューされた、あの戦後混乱の時期に出された『修正資本主義と社会連帯主義』、あれを読んだ時の感動を、いまも忘れてはおりませんよ(笑い)……。
中曽根ありがとうございます(笑い)。
飯塚すごい本を書かれているんだが、あの思想を貫いていくとかつてドイツのアデナウアーがつくったボン憲法の理論を先取りすべきだと、そういうことも言えますね。
ドイツの場合、戦後、「経営組織法]という法律がつくられ、従業員5人以上抱えている経営者は、毎月1回、貸借対照表と損益計算書と営業報告書をつくって、従業員の代表に「こうなってるんだ」ということを、キチッと説明する義務が課されている。こんなふうに、私は日本も、そこまで資本主義は修正されていくべきだと思うんです。
本誌日本にも、やっとそういう動きが出てきましたね。
前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次ページ
(6/8)