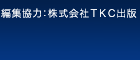ホーム > [飯塚毅博士と私] バンガード対談 > サバイバルの秘訣-2
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
サバイバルの秘訣-2
これからはソフトの勝負
樫尾その通りです。
ハードを作る側も、当然ソフトを考えながらやっているわけですが、使う側のそれぞれの分野の専門家というわけではありませんから、実際に使う側とギャップが出てくるのですね。しかし、それではいけない。おっしゃる通り、これからはソフトの勝負です。
飯塚ところで、カシオさんの電卓を、私は幾つも使わせて頂いています。書斎にも、居間にも置いて。非常に優秀ですね。
樫尾電卓くらいのソフトウェアなら、一般的なものですから問題はないのですが、いま先生がおっしゃった財務会計等に関する計算といった場合は専門的な知識が必要になります。
私たちは、時計にしても、電卓にしても、あるいは楽器にしても、普通の人が喜ばれるようなものを作るのは得意なんですが、1歩進めて専門分野の業務用になると、至らない点が多々あります。それを勉強しなければ、と痛感しています。
飯塚それには絶えざる創造が必要ですね。2、3歩踏み込む、あるいは常識の線を2、3歩踏み出さないと……。
しかし、あの激烈な競争の中から電卓メーカーとして勝ち残られたのは素晴らしい。
いまの関心の的は、パソコンやオフコンですが、各社、髪振り乱してやっていますね。
樫尾それだけ、やはり膨大な需要があるわけで、明るい見通しがあります。
ただ、私のところは、これまで開発指向といっても、どちらかというとユーザーの希望を吸収して喜ばれるものを作ってきたわけですが、そういう形では今ではもう遅れるんですね。お客さんは先々どういうものが欲しいのかを考えてないと……。
先生がさきほどいみじくもおっしゃったように、ソフトについての非常に深い理解、創造性がないとダメだ、という時代に移ってきています。
飯塚なるほど。
樫尾さきほどパソコン、オフコンの話が出ましたが、われわれの浅い知恵でハードを作って、どういう風にお使い下さいますかというのではなく、先生のような専門家が「こういうハードを作れ」ということでないと。
飯塚いや、とんでもない。
しかし、さきほどおっしゃったように、これからは、お客のニーズをきいてから開発するというのでは若干遅いですね。ニーズを先取りする。場合によっては、ニーズを作り出すくらいでないと……。
樫尾そうですね。私どもも、そういうつもりで今日まで歩んできたのです。
ご承知のことですが、計算機の歴史を見ますと、最初は事務用の計算機でした。
会社相手ですから需要は間もなく一巡します。そこで一般家庭でも使えるようなものを作って、需要を広げようということになり、昭和47年に「カシオミニ」を作りました。その次は個人をターゲットにしました。次は個人に1台だけでなく数台持って使って頂く。この考え方で海外にも広く使って頂くと……。
飯塚私の家では、私と家内は別々の電卓を使っています。私が4台、家内も4台。
樫尾電卓は「ニーズを作り出せ」という先生のお話と同じような発想でやりました。
そこまではいいのですが、OA機器になりますと、専門の人たちが実際にどんなものを求めているかは、専門的な知識がないと……。
飯塚専門知識は簡単ですよ。専門書を数多く備えてやれば……。
樫尾専門書だけでは解決できないんじゃないでしょうか。ソフトの創造になりますから。
さっきのお話の1社の会計計算を7分から6秒に短縮するには、専門家が専門のソフトを開発するというのではないとむずかしいのではないですか。
飯塚さきほどの、私も家内も4台ずつ電卓をもっていると申しましたが、実はそれとは別に家庭用のアラーム付電卓を風呂場に置いてあります。何分で風呂に入らねばならないという時のために。洗面所にも置いてあります。いたるところです。私はどうも電卓マニアですね。
樫尾われわれにとっては有難いことです。まあ、それほどに普及したわけですね。おかげ様で。
前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次ページ
(2/8)