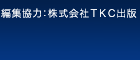ホーム > [飯塚毅博士と私] バンガード対談 > 日本人のユニークさを検証する-2
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
日本人のユニークさを検証する-2
日本人論へのきっかけ
本誌クラークさんのご経歴は、まさにユニークです。
お父上はオクスフォード大学の農業経済研究所長も務めた有名な経済学者。豪州の大学へ移ったので、クラークさんはそこで少年時代を過ごし、オクスフォード大学で民族学と地理学を学ばれた。
豪州の外務省に入って香港、モスクワなどに勤務。硬直した対中国政策に抗議しておやめになった。
飯塚硬骨の士ですね。
本誌労働党政権になって再び外務省に迎えられ、前後4回も訪中しておられます。
その後、日本の対外投資を研究するため来日、『ジ・オーストラリアン』紙東京支局長を経て上智大学教授。
日本語はもちろん、中国語、ロシア語もペラペラ。
飯塚まことに多彩なご経歴。
私は、香港大学からオクスフォード大学に帰られたカービー教授に、福島高商で教わったことがあります。
クラークカービー教授は存じています。
本誌日本に興味を持たれたのは?
クラークモスクワ時代、自分の人生が中国とソ連とのかかわりだけでは面白くないと感じた時からです。
外務省を一時やめて来日、さっき紹介して頂いたように、経済の勉強をしました。それからは日本一辺倒で、中国語の方は忘れました(笑)。
最初に来たのは25年前、香港にいた時です。1週間ほどですが、その時から興味を持ち始めたのです。
飯塚日本人論を書くきっかけは?
クラークきっかけといえば、昭和48年か9年に、外人記者クラブで中根千枝さんが講演したことでした。
飯塚「日本はタテ社会である」と論じた人類学者ですね、中根さんは。
クラーク中根さんはその時、「日本は軟体動物社会である」と説明しました。面白い説明ですね。
私はまず、「軟体動物社会というのは英語に訳しにくい。くらげ=ジェリーフィッシュ社会といったらどうか」と申し上げた。中根さんは、あとでこの言葉を使っていました。
続けて私は、当時は典型的な西欧人のメンタリティーを持っていましたから、「軟体動物社会は遅れた社会、部族(tribe)社会ではないか」と質問したのです。
飯塚なるほど、そこでトライブという発想がうまれた。
クラークそうなんです。さらに「日本というトライブは、いつになればネーション(nation)になるのか」と。
「変わっている」のは外人の方?
飯塚私はいつも「日本人には原理・原則がない」と慨嘆しているのですが、同じようなご指摘ですね。
ネーションは国家とも民族とも訳されますが、この場合はどちらが合いますか。
クラーク私の頭の中では、国家の方が近いですね。
中根さんは、私の質問に対し、「部族というような悪い組織でない」と、ご立腹でしたが(笑)。
これが機縁で日本と日本人をどう把えるか、突っ込んで考え始めたのです。
飯塚さすが、学者の家系だ。
クラークいろんな説を検討してみましたが、どうもぴったりこない。
しかし、日本人が非常に他と違ったユニークな存在であるという事実は、厳然として目の前にある。
この謎をどう解くか、悩みました(笑)。
飯塚ハッハッハ。そこがクラークさんのユニークなところですよ。
実は私も、若い時は「人生とは何か。いかに生きるべきか」と悩み、禅と哲学に打ち込んだ時期がありました。あの時も、首尾一貫した答えを求めていたと思います。
いずれにせよ、ご苦労さまでした。本来は日本人自身が考え、外国の方に提示すべきなんですが、日本人にはその用意がなかった。
それで?
クラーク多くの説を検討しても生産的な結果が出るとは思えない、という結論に達した時、ひらめいたのです。
「AがX、Y、Zと異なるとき、Aに何かがあったのだ、と考えるしかないのだろうか。X、Y、Zの方に何かがあって、その結果Aと違ってしまった、と考えることも出来るのではないか」
つまり、「変わっている」のは日本人の方でなく、われわれ非日本人ではないか。
本誌コペルニクス的転換ですね(笑)。
クラーク日本人が日本人的であるのは、かれらに何かが起こらなかったからである。
他方、他の多くの国民には何か非常に重要で心に傷を残すようなことが起こり、それが国民性に影響を与えているのではないか。
それは何か。幕末の開国まで、日本人は人種的に異なる相手と、重大な、あるいは長期的な抗争――戦争に巻き込まれなかった、ということではないか。
飯塚そう。蒙古襲来と秀吉の朝鮮出兵があるが、これは一過性のものです。朝鮮出兵は正確にいえば侵略で、向うには大変な傷を与えたが、こちらはケロリ。戦前の教科書には「朝鮮征伐」とあったほどです。
本誌相手に与えた傷には思い及ばないというか、忘れっぽいですね、日本人は。
戦争の舞台にして荒らした国へ、元軍人が団体で行き、戦死した仲間を偲ぶ。そこまではよいとしても、慰霊碑を建てるに至っては無神経といわざるを得ない。
これも、いまのお話のように、第2次大戦で負けるまで、他人種から傷を負った経験がほとんどないからですね。
前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次ページ
(2/8)