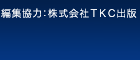ホーム > [飯塚毅博士と私] バンガード対談 > 日本人のユニークさを検証する-5
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
日本人のユニークさを検証する-5
アングロサクソンと日本人
飯塚クラークさんがそのお1人であるアングロサクソンは、偉大な民族ですね。
世界を変えた産業革命の創始者という一事を考えても。
クラーク昔はそうでしたが、今はだめになりました。私は悲観的です。
50年ほど前から変わった。それまでは、日本と同じように、1つの会社や組織に忠誠心があって、簡単に他の会社へ移ったりしませんでした。会社でも工場でもよく協力しました。日本人のようにね。
飯塚50年前というと、第1次大戦のあとですね。
クラークええ。それまでは英国人は応用技術に強かったんですが、いまの若い人はエンジニアになりたがらない。純粋科学というか理論的な研究を望みます。ビジネスよりも弁護士や会計士ね。製造業、とくに工場へはほとんどゆかない。
飯塚ヨーロッパは第1次大戦で大きく変わったんですね。19世紀以来の「人類は無限に進歩する」という楽観主義が、あそこで挫折し、自らの文明への幻滅と懐疑に悩むようになった。これも私の愛読書であるシュペングラーの『西欧の没落』は、その状況の中から生れたのです。
日本は、第1次大戦ではほとんど戦わないで、金と領土――南洋群島――を獲得し、5大国の1つに成り上がった。ヨーロッパとは反対でした。
その代わり、第2次大戦は完全敗北で、初めて外国の軍隊に占領され、旧秩序が崩壊した。第1次大戦がヨーロッパに対してもったのと同じ作用があった。
クラーク仰言る通りです。
『西欧の没落』を愛読書にされるとは、飯塚さんは余程、ヨーロッパに親近感を持っていらっしゃるのですね。
本誌飯塚会長の親ドイツとアングロサクソン文化への畏敬は、大変なものです。
飯塚学生時代は、さっき申したように、ドイツの哲学に親しみ、英国の法律や会計学を学びましたからね。
陸軍にとられて駆け出し将校の時代にも、連隊長に申告してオクスフォード大学の法学のテキストを取り寄せ、勉強したものです。
クラークあの時代の日本の軍隊で、そんなことが出来たとは驚きです(笑)。
飯塚いや、「敵に勝つには敵を知らなければならない」と、孫子の兵法を大義名分にしたのです。いわば作戦勝ち(笑)。
クラーク飯塚さんはまさにユニークな日本人だ(笑)。
以心伝心で運営する英国憲法
飯塚いま、人類の4分の1は中国人で、中国語人口が1番多いかもしれないが、世界の共通語といえばやはり英語です。
それに議会制度、会計制度、いま日本の演劇界で大変なブームのシェークススピア――ちょっと数えただけでもアングロサクソン民族の産み出した文化は、知的社会で支配的というか卓越性を示し、われわれは大変な恩恵を受けています。
クラークさんはさっきから控え目に話していらっしゃるが(笑)。
本誌冷厳に現実を見る能力――これもアングロサクソンのお家芸ではないですか。
クラークいま、飯塚さんが知的社会と言われましたが、アングロサクソンの特性は知的というより現実的な知恵だと思います。
議会制度もその現れです。しかも憲法なしにそれを運営しています。
つまり、以心伝心でやっている。
飯塚憲法がないと仰言るが、文章化されていないだけで、実体はちゃんとある。ダイシーやバジョットが『English Constitution』を書いていますね。
クラークそうです。成文法ではなく慣習法なんです、イギリス憲法は。フランス人やドイツ人はちゃんと条文化された憲法でないと気がすまないけれど(笑)。
飯塚学生時代、ロンドン大学出身のゲェティンビーという先生から英語を教わりましたが、ある日、先生に尋ねたのです。
「アングロサクソンが偉大な民族であることは分かった。では、アングロサクソンのオリジナルなものは何か」と。
先生、しばらく立往生したあと、
「そういわれると、クリケットとパーラメンタリズム(議会主義)くらいかもしれない」という答えでした。
クラーク名答ですね。立往生した割りには(笑)。
本誌クリケットというのはゲームでしょう?それと議会主義を対にしたところにユーモアがある。
飯塚「では、日本のオリジナルは何か」と反問されると、困るんだなあ。
クラーク先生流にいうと、
「部族社会の人間関係原理の温存」
ということになるが、クリケットのようにうまく対になり、かつユーモアを感じさせるようなものは何だろう。
本誌オリジナルというなら相撲がありますが、ユーモアになりませんね(笑)。
前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次ページ
(5/8)