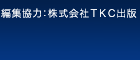ホーム > [飯塚毅博士と私] バンガード対談 > 日本人のユニークさを検証する-3
(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』386頁)
日本人のユニークさを検証する-3
北欧人と日本人の意外な共通性
飯塚要するに、そうした幸運のおかげで日本人はトライブ――部族時代のエモーション(感情)を、民族になり国民になった段階でもほとんど変えずに保存することができ、現在に至っている。
それに対し、たとえばクラークさんが属する西欧人は、同じくトライブから出発して、民族になり国民になったが、その途中、あるいはその後、異人種、異民族ないし国家と深刻な抗争を経験して、トライブ時代のエモーションから逸脱していった。
お説はそういうことですね。
クラークそうです。
飯塚この「逸脱」という表現に私は印象を受けたのです。クラークさんは、それを民族ないし国家として持つに至ったイデオロギーの強弱と結びつけておられますね。
クラーク日本の場合は、地理的環境に恵まれたため平和で、イデオロギーの必要がなかった。古代に中国からイデオロギーを取り入れましたが、一時的なものに終わりました。
人々の発想がムラ的、家族的なまま推移したのはそのためです。
私もその1人である北ヨーロッパ人も、かつてはそうした日本人と似ていたのですよ。
飯塚ほう。北欧人が?
クラーク北欧は、かつてはヨーロッパの僻地だったので、古代、中世には日本と同じようにムラ社会、封建社会でした。
飯塚そしてクラークさんのいう人間関係社会だった。
クラークそう。そこへ南ヨーロッパの合理主義が入ってきたのです。その組み合わせで工業社会ができ上がった。
南ヨーロッパ人は、頭はいいけれど協調性がない。
飯塚確かに人間関係的でない。
私が若い時から親しんだドイツ観念哲学は、北の人間関係社会と南の合理主義を融合しようという壮大な努力といえるかもしれませんね。だから一時期、同じような問題を抱えていた日本人の心を捉えたのではないか。
クラークそうかもしれません。
部族社会――人間関係社会のメンタリティーを保存している日本人に近いのは、北欧人の中でもドイツ人とイギリス人です。
イギリス人は島国のため、ドイツ人は民族国家としての成立が遅れていましたから。
飯塚ビスマルクによるドイツ統一は1871年。明治維新の方が3年早かったんだ。
クラークだから、仕事に対する素朴な責任感とか情緒性では、日本に通ずる所があるでしょう。
飯塚TKCは西独の同業ダーテフ社と提携していますが、その交流を通じ、いま先生が言われたことを、私は実感しています。
クラークドイツの文化はエモーショナル=情緒性の強い文化です。
飯塚私が愛読してきたゲーテの代表作は『ファウスト』と並んで『若きヴェルテルの悩み』ですし、ベートーベンを頂点とするロマン派の音楽をとっても、それは分かります。
しかし、同時にドイツの法制、とくに税制の周到さ、厳密さを思うと、わが日本とは雲泥の差で、私はいつも歯ぎしりしています。日本の当局に対してですがね。
前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次ページ
(3/8)